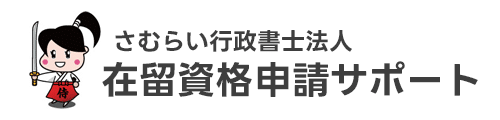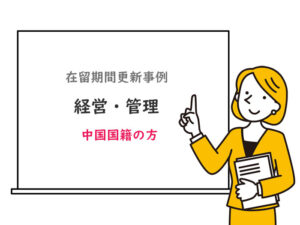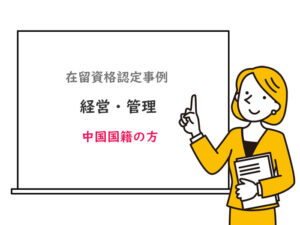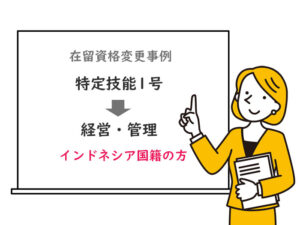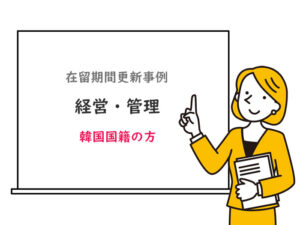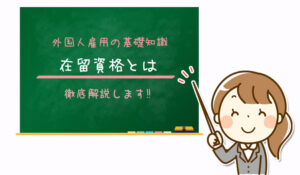「自分の国に日本製品を輸出する会社を日本で作りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その場合、「経営管理」という在留資格が必要になります。(在留資格に関しては『在留資格とは』で詳しくご説明しておりますので、ご参照下さい。)
「経営管理」という在留資格がどういったもので、どのように申請をするのかのポイントをわかりやすくご説明したいと思います。
経営管理ビザの基本
まずはじめに、経営管理ビザが一体どのようなものなのか、その本質をしっかりと掴むところから始めましょう。
「経営管理」の3つの活動パターン
経営管理ビザは、正式には在留資格「経営・管理」と呼ばれます。
このビザは、外国人が日本でビジネスの舵取りを行うために不可欠なキーです。
具体的に許可されている活動は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
【活動パターン1】新規事業の開始(日本で会社を設立し、その経営を行う)
これが最も一般的な、いわゆる「起業家」のパターンです。
自分で会社を設立し、社長(代表取締役)として事業をゼロから立ち上げる活動がこれに該当します。
飲食店、貿易会社、ITサービスなど、事業内容は多岐にわたります。
【活動パターン2】既存事業への参画(日本の会社に出資し、その経営に参加する)
すでに日本にある会社に投資(株式の取得など)を行い、役員として経営に加わるパターンです。
例えば、後継者を探している中小企業の経営を引き継いだり、成長中のベンチャー企業に役員として参画したりする場合が考えられます。
【活動パターン3】経営の代行(事業の管理者に就任する)
自ら出資や起業をするのではなく、既存の会社の経営者(オーナーなど)に代わって、事業の管理に従事するパターンです。
これには、日本法人の支店長や工場長、あるいは本社の部長クラスといった管理職としての活動が含まれます。
このように、経営管理ビザがカバーする範囲は広く、創業者である「経営者」だけでなく、会社の運営に実質的に関与する「管理者」も対象となります。
具体的には、代表取締役、取締役、監査役といった役員から、部長、支店長、工場長といった上級管理職までがこのビザの取得対象者です。
「投資・経営」から「経営・管理」への変更の背景
現在の「経営・管理」という名称は、実は2015年の法改正によって生まれたものです。
それ以前は、「投資・経営」という名前の在留資格でした。
この変更は、単なる名称の変更ではなく、日本の経済戦略の転換を象徴する重要な意味を持っています。
旧制度「投資・経営」
この時代のビザは、その名の通り「外国からの投資」が前提でした。
つまり、外国資本が日本に投入されることが、ビザ取得の大きな要件だったのです。
これは、日本が海外からの「お金」を呼び込むことに主眼を置いていたことを示しています。
新制度「経営・管理」
2015年の改正で、この「外国資本による投資」という要件が撤廃されました。
これにより、日本国内の資本だけで設立された会社(純粋な日系企業)であっても、外国人がその経営や管理に従事できるようになったのです。
この変化の裏には、日本の経済が直面する課題と、それに対する戦略のシフトがあります。
少子高齢化が進む中で、日本は単に海外からの「資本」を求めるだけでなく、グローバルな視点を持つ優秀な「経営人材」そのものを求めるようになりました。
革新的なビジネスモデルや国際的なネットワークを持つ外国人の経営手腕を、国内企業の成長に活かしてほしい、という国の意思の表れなのです。
この制度変更は、起業家にとって大きなチャンスを意味します。
審査において、資金の出所が海外か国内かは問われなくなりました。
それよりも、経営者としてのスキル、経験、そしてこれから展開するビジネスの質が、より一層重視されるようになったのです。
経営管理ビザの3つの要件
経営管理ビザの申請は、単なる書類の提出作業ではありません。
それは、あなたのビジネスが「本物」であることを証明するプロセスです。
入国管理局の審査官は、あなたのビジネスが日本で安定して継続していけるのかを、3つの大きな柱で判断します。
それが「事業所」「事業規模」「事業計画」です。
【第1の要件】事業所の確保
なぜ、事務所の要件はこれほど厳しいのでしょうか。
それは、事務所があなたのビジネスの「実体性」を証明する、最もわかりやすい物理的な証拠だからです。
審査官は、ペーパーカンパニーではなく、実際に事業活動が行われる拠点が存在することを確認したいのです。
契約の基本ルール
事務所の賃貸借契約には、絶対に外せない2つのルールがあります。
契約名義は「法人名義」であること
契約者は、あなた個人ではなく、設立する会社(法人)でなければなりません。
しかし、会社設立前は法人名義で契約できないのが一般的です。
そのため、実務上は「まず代表者個人の名義で契約し、会社設立後に法人名義に切り替える」という手順を踏みます。
この際、必ず契約前に家主や不動産会社に「法人設立後に名義変更が可能か」を確認し、承諾を得ておくことが不可欠です。
使用目的は「事業用」であること
契約書の使用目的欄が「居住用」となっている物件は、原則として事務所として認められません。
必ず「事務所」や「店舗」など、事業目的での使用が明記されていることを確認してください。
物理的な要件
契約書だけでなく、事務所そのものにも実態が求められます。
- 看板・表札(社名表示): 誰が見てもそこがあなたの会社だとわかるように、入口や集合ポストには会社の名前を掲示する必要があります。
- 独立した郵便受け: 会社の郵便物を確実に受け取れる体制も必要です。
- 事業に必要な設備: 机、椅子、パソコン、電話、インターネット回線など、すぐにでも事業を開始できる設備が整っている状態が求められます。申請時には、これらの設備が設置された事務所内外の写真を提出し、事業の実態を証明します 13。
事務所タイプの比較表
事務所選びは、ビザ申請の成否を分ける最初の関門です。
誤った物件を契約してしまうと、時間もお金も無駄になりかねません。
以下の表で、どのタイプの事務所が適切か、一目で確認してください。
| 事務所タイプ | 許可の可能性 | 注意点・条件 |
| 一般の賃貸オフィス | ◎ (Excellent) | 最も確実で推奨される選択肢。契約書の内容をしっかり確認することが重要。 |
| レンタルオフィス(個室) | ○ (Good) | 施錠可能な独立した個室であることが絶対条件。 壁で完全に仕切られ、プライバシーが保たれている必要があります。 オープンな共有スペースのみのプランは不可です。 |
| 自宅兼事務所 | △ (Conditional) | 非常にハードルが高いです。 戸建てで、居住スペースと事業スペースが玄関や階段などで完全に分離されている場合のみ、例外的に認められる可能性があります。 一般的なマンションやアパートでは原則として認められません。 |
| コワーキングスペース | × (Not Permitted) | 独立性・排他性がなく、事業の拠点として認められません。 不特定多数とスペースを共有するため、経営管理ビザの要件を満たしません。 |
| バーチャルオフィス | × (Not Permitted) | 住所貸しサービスであり、事業を行う物理的な実体がないため、絶対に認められません。 経営管理ビザ申請における典型的な失敗例です。 |
事務所の要件が厳しいのは、単に働く場所を求めているからではありません。
月単位の短期契約ではなく年単位の長期契約を求め、法人名義での正式な契約を要求するのは、入国管理局があなたの「本気度」を測っているからです。
事業開始前から相応の金銭的・法的なコミットメントができる申請者は、事業への覚悟が固く、成功の可能性も高いと見なされます。
つまり、事務所の確保は、あなたのビジネスへの「コミットメント・テスト」なのです。
【第2の要件】事業規模の証明
次に、一定の規模を持つビジネスであることを証明する必要があります。
その証明方法は、主に2つあります。
【方法1】資本金500万円以上の投資
これは、新規起業家が最も一般的に選択する方法です。
会社設立時に資本金を500万円以上に設定することで、事業規模の要件を満たします。
しかし、ここで最も重要なのは、単に500万円という金額を用意することではありません。
審査官が最も厳しくチェックするのは、その500万円を「どのようにして」形成したかという「資産形成過程」です。
自分の給料から貯めた場合
最もクリーンで説明しやすいパターンです。給与の振込や、毎月少しずつ残高が増えていく様子がわかる、過去数年分の預金通帳のコピーを提出します 25。併せて、在職証明書や給与明細、納税証明書などで、その収入が合法的な労働によるものであることを証明します 28。ある日突然、口座に500万円が振り込まれているような履歴は、「見せ金」を疑われる最大の原因となります。
親族から借りた、または贈与された場合
これもよくあるケースですが、非常に丁寧な証明が求められます。
- 金銭消費貸借契約書(借用書): 借金の場合は、返済期間や利息などを定めた正式な契約書が必要です。
- 送金記録: 親の口座からあなたの口座へ、契約書通りの金額が振り込まれたことを証明する銀行の取引明細が必須です。現金での手渡しは、金の流れが追えないため避けるべきです。
- 貸主・贈与者の資力証明: これが非常に重要です。そのお金を貸したり、あげたりした親族に、それだけの金銭的余裕があったことを証明する必要があります。親族自身の預金通帳のコピーや所得証明書などの提出が求められることもあります。
資産(不動産や株など)を売却した場合
その売買契約書や、売却代金が振り込まれたことがわかる銀行の取引明細などを提出します。
絶対に避けるべき「見せ金」
「ビザ申請の時だけ、一時的にお金を借りて口座に入れ、許可が下りたらすぐに返す」という行為は「見せ金(みせがね)」と呼ばれ、違法です。
これは入国管理局の審査で必ず見抜かれます。
発覚した場合、ビザが不許可になるだけでなく、虚偽申請として記録が残り、将来のビザ申請にも深刻な悪影響を及ぼします。
資本金は、実際に事業を運営するために使う、正真正銘の事業資金でなければなりません。
【方法2】 常勤職員2名以上の雇用
もう一つの方法は、500万円の資本金の代わりに、常勤の職員を2名以上雇用することです。
- 「常勤職員」の定義:パートやアルバイト、業務委託契約者ではなく、正社員として直接雇用し、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している必要があります。労働時間もフルタイム(週30時間以上が目安)であることが求められます。
- 国籍・在留資格の要件:この要件で最も注意すべき点は、雇用する職員の国籍や在留資格です。カウントできるのは、日本人、特別永주者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限られます。あなたと同じように「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く外国人は、この2名の数に含めることはできません。
資本金500万円という要件は、単なる数字合わせではありません。
これは、日本で小規模なビジネスを立ち上げ、軌道に乗るまでの運転資金(家賃、給料、諸経費)として最低限必要だと考えられている金額です。
そして、その資金の出所を厳しく問うのは、マネーロンダリングなどの不正を防ぐと同時に、申請者の「過去」を評価するためでもあります。
自力で正当に500万円を蓄財できた人物は、それだけの計画性や規律、遂行能力を持っており、経営者としても成功する可能性が高い、と判断されるのです。
つまり、資本金は、ビジネスの「未来」の存続可能性と、あなた自身の「過去」の信頼性を同時に証明する、重要な指標なのです。
【第3の要件】事業計画書
「事業計画書」は、提出する書類の中で最も重要と言っても過言ではありません。
なぜなら、事業計画書は、ビジネスが「安定的・継続的」に運営可能であることを、審査官に具体的に語りかける唯一の手段だからです。
どんなに事務所が立派で、資本金が十分にあっても、この計画が稚拙であればビザは許可されません。
成功する事業計画書の構成要素
審査官の心を動かす事業計画書には、説得力のあるストーリーが必要です。
以下の要素を盛り込み、具体的かつ論理的に記述しましょう。
- 創業の動機: なぜ、あなたはこのビジネスを日本で始めたいのですか? あなた自身の経験やスキル、情熱が、この事業にどう結びついているのかを語ってください。これは計画書の肝となる部分です。
- 事業の概要: 具体的に何をする会社なのかを簡潔に説明します。どのような商品やサービスを、誰に提供するのか。ビジネスモデルの全体像を示します。商品がある場合は、写真などを加えるとより伝わりやすくなります。
- 自社の強みと市場分析: 競合他社と比べて、あなたのビジネスの強みは何ですか? あなたの持つ特別な技術、独自のネットワーク、あるいはニッチな市場への着眼点などをアピールします。なぜこの事業が市場で成功できるのか、客観的なデータ(市場規模など)を交えて説明できると説得力が増します。
- 販売戦略・集客方法: どのようにして顧客を見つけ、商品を販売しますか? 具体的なマーケティング手法(SNS、ウェブサイト、広告など)を記述します。
- 仕入先・販売先: すでに具体的な取引先候補がいる場合は、その情報を記載しましょう。もし、基本合意書や見積書などがあれば、それは事業の実現可能性を示す強力な証拠となります。
- 収支計画(損益計画書): これが計画書の「心臓部」です。今後1〜3年間の売上、原価、経費、そして利益の見込みを具体的な数字で示します。重要なのは、それぞれの数字に「なぜそうなるのか」という明確な根拠があることです。「なんとなくこれくらい売れそう」という希望的観測ではなく、「客単価 × 客数 × 営業日数」のように、論理的に積み上げた数字でなければなりません。
- 人員計画: いつ、どのような人材を何人採用する予定なのかを記載します。
「貿易業をやります」といった漠然とした計画では、審査官は何も判断できません。
「どの国の、どの企業から、何を仕入れ、日本のどの層の顧客に、どのような方法で販売し、どれくらいの利益を見込むのか」というレベルまで具体化することが求められます。
あなたは、申請プロセスにおいて審査官と直接会って話す機会はほとんどありません。
この書類を通じて、あなたの経営者としての能力、先見性、そして事業への真剣な姿勢を伝えるのです。
審査官が抱くであろう「このビジネスは本当に儲かるのか?」「この申請者は信頼できる人物か?」といった疑問に、先回りして答えるつもりで作成することが、成功への鍵となります。
申請からビザ取得までの全手順
経営管理ビザの取得は、周到な準備と計画的な手続きが求められる長丁場です。
ここでは、日本国内から申請する場合の標準的な流れと、海外からの挑戦を可能にする「4ヶ月ビザ」の特別な流れを、ステップごとに解説します。
標準的な申請フロー(日本在住者向け)
すでに留学や就労など、何らかの在留資格で日本に住んでいる方が、経営管理ビザへ変更する場合の一般的な流れです。
全体の所要期間は、準備開始から許可までおよそ4ヶ月から6ヶ月を見込んでおくと良いでしょう。
- 事業計画の策定と事業所の契約(約1〜4週間)まずは、先程解説した事業計画を練り上げ、事業の核を固めます。同時に、要件を満たす事務所(オフィス)を探し、賃貸借契約を締結します。
- 会社設立手続き(約2〜4週間)事業の器となる会社を設立します。司法書士などの専門家と連携しながら、以下の手続きを進めます。
- 定款の作成・認証: 会社のルールブックである定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
- 資本金の払込: あなた個人の銀行口座に、発起人として資本金(500万円以上)を振り込みます。
- 法務局への登記申請: 必要書類を揃え、法務局に会社設立の登記を申請します。登記が完了すると、会社が法的に誕生します。
- 各種行政手続き(約1〜2週間)会社設立後、速やかに税務署や都道府県、市町村へ開業に関する届出を行います。特に税務署に提出する「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」の控えは、ビザ申請の必須書類です。
- 営業に必要な許認可の取得(事業による)もしあなたの事業が、飲食店(飲食店営業許可)、不動産業(宅地建物取引業免許)、旅行業(旅行業登録)など、行政の許可や認可が必要な業種である場合、ビザ申請の前に必ずその許認可を取得しなければなりません。許認可がない状態でビザを申請しても、事業が適法に行えないため不許可となります。
- 経営管理ビザの申請書類作成・提出(約1ヶ月)これまでに揃えた全ての書類(登記事項証明書、定款、事務所の契約書、許認可証、事業計画書など)をまとめ、出入国在留管理庁(入管)に在留資格変更許可申請を行います。
- 入管による審査(約1〜3ヶ月)申請後、審査官による審査が行われます。審査期間は申請内容や時期によって変動しますが、通常1〜3ヶ月程度かかります。この間、追加資料の提出を求められることもあります。
- 許可・新しい在留カードの受領無事に審査を通過すると、許可通知が届きます。入管で手続きを行い、新しい在留資格「経営・管理」が記載された在留カードを受け取れば、晴れて日本での経営活動をスタートできます。
海外からの挑戦を可能にする「4ヶ月ビザ」とは?
「日本に協力者がいない」「まだ日本に住んでいない」という海外在住者にとって、上記のプロセスは非常に困難でした。
なぜなら、短期滞在ビザでは日本の銀行口座開設や会社登記ができず、身動きが取れなかったからです。
この問題を解決するために、2015年に「4ヶ月の経営管理ビザ」という特別な制度が創設されました。
これは、海外にいる申請者が、まず会社設立などの準備活動を行うために日本に入国・滞在することを許可する、いわば「準備期間のため」のビザです。
「4ヶ月ビザ」を利用した申請フロー
- 海外での準備日本国外で、事業計画書と会社の定款案を作成します。この段階では、まだ事務所の賃貸借契約は不要ですが、候補となる物件の資料などを準備し、事務所を確保する見込みがあることを示します。
- 「4ヶ月」の在留資格認定証明書を申請作成した事業計画書や定款案などを日本の入管に提出し、「4ヶ月」の経営管理ビザの在留資格認定証明書を申請します。
- 在留資格認定証明書受領後、それを持って自国の日本大使館・総領事館でビザの発給を受け、日本へ入国します。空港で「経営・管理 在留期間4月」と記載された在留カードが交付されます。
- 在留期間である4ヶ月以内に、以下の全てを完了させる必要がありますので、迅速に行動する必要があります。
- 住民登録、印鑑登録
- 日本での銀行口座開設
- 事務所の正式な賃貸借契約
- 資本金の払込
- 法務局での会社設立登記
- 在留期間更新許可申請4ヶ月の期限が切れる前に、設立した会社の登記事項証明書や正式な事務所の契約書など、全ての準備が整ったことを証明する書類を揃え、通常の「1年」の経営管理ビザへの更新を申請します。
4ヶ月ビザのメリットと注意点
- メリット: 海外にいながら、日本に協力者がいなくても起業プロセスを開始できる点です。また、ビザの許可が出るか不確かな状態で、数ヶ月分の事務所家賃を払い続けるリスクを軽減できます。
- 注意点(デメリット): 4ヶ月という期間は非常にタイトです。特に外国人にとって、短期の在留資格で住居や事務所の契約をすることは困難を伴う場合があります。もし期間内に全ての準備を完了できなければ、ビザは更新されず、帰国せざるを得なくなる可能性があります。
必要書類リスト(新規設立・カテゴリー4の場合)
経営管理ビザの申請では、所属する会社(機関)が規模などによって4つの「カテゴリー」に分類され、それに応じて提出書類の量が異なります。
上場企業などはカテゴリー1に該当し、提出書類が大幅に簡素化されますが、
あなたがこれから設立する新しい会社は、ほぼ間違いなく最も多くの書類が求められる「カテゴリー4」に該当します。
以下は、出入国在留管理庁が公表している情報を基にした、新規設立会社(カテゴリー4)が在留資格認定証明書を申請する際の、代表的な必要書類リストです。これらを漏れなく、かつ丁寧に準備することが許可への第一歩です。
【申請者に関する書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真(規定サイズあり)
- 返信用封筒(切手貼付)
- 履歴書(学歴、職歴を詳細に記載)
- (管理者の場合)経営・管理に関する3年以上の経験を証明する文書(在職証明書など)
【会社に関する書類】
- 事業計画書: 事業の安定性・継続性を証明する最重要書類。
- 定款の写し: 会社設立時に作成したもの。
- 法人の登記事項証明書: 会社設立後に法務局で取得。
- 会社案内: 会社のパンフレットやウェブサイトのURLなど、事業内容がわかるもの。
- 株主名簿: 誰がどれだけ出資しているかを示すリスト。
【事業所(事務所)に関する書類】
- 不動産の登記事項証明書(自社所有の場合)または賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)。契約書は法人名義で、使用目的が「事業用」であることが必須。
- 事務所の写真:
- 建物の外観
- 会社の表札や看板が確認できる入口の写真
- 郵便受けの写真
- 事務所内部の写真(机、椅子、PC、電話などの備品が設置されている様子がわかるもの)
【財務・規模に関する書類】
- 資本金の形成過程を証明する資料:
- 申請者個人の預金通帳のコピー(給与振込や貯蓄の履歴がわかるもの)
- 親族などから借りた場合は、金銭消費貸借契約書、送金記録、貸主の資力証明書など。
- 法人設立届出書の控えの写し: 税務署の受付印があるもの。
- 給与支払事務所等の開設届出書の控えの写し: 税務署の受付印があるもの。
- 直近3ヶ月分の源泉所得税の納付書(領収日付印のあるものの写し) または 納期の特例の承認に関する申請書の控えの写し
これはあくまで基本的なリストです。
あなたの事業内容や個別の状況によって、これ以外の追加資料の提出を求められることもあります。
経営管理ビザ取得後の更新
ここでは、ビザ取得後の更新に関してのポイントを解説します。
初回の在留期間は1年?
苦労して経営管理ビザを取得したのに、在留期間が「1年」でがっかりした、という話はよく聞きます。
しかし、これは標準的な扱いですので安心してください。
初めて事業を立ち上げた会社が、本当に計画通りに運営され、日本経済に貢献できる存在になるかどうかは、誰にもわかりません。
日本の起業生存率を見ても、5年後まで存続している会社は約4割という厳しい現実があります。
そのため、入国管理局はまず「1年間、様子を見せてもらいましょう」というスタンスを取ります。
この1年間は、あなたの経営手腕が試される、いわば「お試し期間」です。
運転免許を取得したばかりの人が、最初は有効期間の短い免許証を渡されるのと同じイメージです。
この1年間の経営実績が評価されれば、次の更新で3年、そして5年と、より長期の在留期間が許可される道が開けていきます。
事業の継続性と会社の業績
1年後の更新申請で、審査官が最も重視するのは「事業が健全に継続しているか」という点です。
最初の申請では「事業計画書」という未来の約束が評価の中心でしたが、更新では「決算書」という過去1年間の実績が全てを物語ります。
赤字決算の場合
特に起業1年目は、事務所の初期費用や設備の購入など、投資が先行するため赤字決算になることは珍しくありません。
この点については、入国管理局もある程度理解を示してくれます。
しかし、単に「赤字でした」では通用しません。
なぜ赤字になったのかという合理的な理由と、来期以降どのようにして黒字化していくのかという具体的な改善策を示した「事業改善計画書」を提出することが、更新の許可を得るために不可欠です。
【注意すべき危険信号】
- 2期連続の赤字: 1年目の赤字は許容されても、2年目も赤字となると、事業の継続性に深刻な疑問符が付きます。
- 債務超過: 会社の負債が資産を上回っている状態です。これは会社の体力が尽きかけているサインであり、更新が極めて困難になる重大な危険信号です。
役員報酬の設定
ビザの更新において、多くの経営者が陥りがちなジレンマが「役員報酬」の設定です。
「会社の利益を出すために、自分の給料(役員報酬)を低く抑えたい」と考えるのは自然なことです。
しかし、これがビザ更新の大きな落とし穴になり得ます。
役員報酬を極端に低く設定する(あるいはゼロにする)と、審査官はこう考えます。
「この経営者は、この収入でどうやって日本で生活しているのだろう?」「事業がうまくいっておらず、十分な報酬を払えないのではないか?」「あるいは、申告していない別の収入源(不法就労)があるのではないか?」。
このような疑念を抱かせないため、役員報酬には「生活給」としての下限が存在します。
- 推奨される最低ライン: 月額18万円〜20万円以上が、実務上の目安とされています。これは、独身者が日本で最低限の生活を営むために必要な金額と考えられています。
- 家族を扶養する場合: 配偶者やお子さんがいる場合は、当然ながらより高い報酬設定が求められます。
- 将来の永住を見据えるなら: 将来的に永住許可申請を考えているのであれば、安定した生計を証明するためにも、年収300万円(月額25万円)以上を目指すのが賢明です。
また、従業員を雇用している場合、経営者であるあなたの役員報酬が、その従業員の給与よりも低いというのは不自然です。
経営者としての責任と役割に見合った、そして日本で安定した生活を送れるだけの報酬を、会社の経費として適切に計上することが、事業の健全性を示す上で非常に重要なのです。
他の就労ビザとの違い
「自分は本当に経営管理ビザで合っているのだろうか?」——そう疑問に思う方もいるかもしれません。
外国人が日本で働くためのビザ(在留資格)には様々な種類があり、それぞれ目的や要件が異なります。
特に、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「高度専門職」ビザとの違いを理解することは、あなたが正しい道筋を歩むために重要です。
以下の比較表で、それぞれのビザの役割の違いを明確にしましょう。
主要な就労ビザの比較
| 項目 | 経営・管理 | 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職(経営・管理活動) |
| 主な活動内容 | 会社の経営・管理。事業の意思決定を行う。 | 会社との契約に基づき、専門的な知識や技術を活かした業務に従事する(エンジニア、通訳、マーケターなど)。 | 経営・管理活動のうち、ポイント制で高く評価される高度な活動。 |
| 求められる立場 | 経営者・管理者(雇う側) | 従業員(雇われる側) | 高度な経営者・管理者 |
| 資本金要件 | 原則500万円以上(または常勤職員2名以上)。 | なし | 経営管理ビザの要件を満たす必要がある。 |
| 学歴・職歴要件 | 経営者には必須ではない。ただし管理者の場合は3年以上の関連経験が必要。 | 原則、関連分野の大学卒業または10年以上の実務経験が必要。 | ポイント計算の重要項目であり、高学歴・高年収・長い職歴が有利。 |
| 家族の就労 | 配偶者は「家族滞在」ビザで、原則週28時間以内の就労に制限される。 | 同上 | 一定の条件下で、配偶者のフルタイム就労が可能。 |
| 永住権への道 | 原則として日本に10年以上在留が必要。 | 原則として日本に10年以上在留が必要。 | ポイントに応じて、最短1年または3年の在留で永住申請が可能になる優遇措置がある。 |
この表からわかる最も根本的な違いは、「経営・管理」ビザが「雇う側(経営者)」のためのビザであるのに対し、「技術・人文知識・国際業務」ビザは「雇われる側(従業員)」のためのビザであるという点です。(※詳しくは『在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」をわかりやすく説明します』をご参照下さい)
この立場の違いが、全ての要件の違いに繋がっています。
「経営者」は、事業を立ち上げ、雇用を生み出す責任があるため、事業そのものの健全性(資本金、事業所、事業計画)が問われます。
一方、「従業員」は、特定の業務を遂行する能力があることを証明する必要があるため、個人のスキル(学歴、職歴)が問われるのです。
そして「高度専門職」ビザは、これらの活動を行う人々の中でも、特に優秀な人材(高度人材)を日本に誘致するための、いわば「VIPパス」です。
経営管理ビザの要件を満たした上で、さらに学歴、職歴、年収などで算出されるポイントが一定基準(70点以上)に達した場合に取得でき、永住権申請期間の短縮など、様々な優遇措置が受けられます。(※詳しくは『在留資格「高度専門職」|高度専門職を分かりやすくご説明します』をご参照下さい)
あなたが会社の方向性を決め、事業のリスクを負い、従業員を率いていく立場を目指すのであれば、選ぶべき道は「経営・管理」ビザです。
よくある質問 (FAQ) と専門家への相談
ここまで経営管理ビザの全体像を解説してきましたが、実際の申請準備を進める中では、さらに細かな疑問や不安が出てくることでしょう。
ここでは、私たちが日々の相談で特によく受ける質問にお答えします。
Q1: 複数人で会社を経営したいのですが、全員がビザを取得できますか?
A: 可能性はありますが、非常にハードルが高くなります。
複数の外国人が共同経営者としてそれぞれ経営管理ビザを申請する場合、入国管理局は「なぜ、この規模の事業に複数の経営者が必要なのか」という合理的な理由を厳しく審査します。
成功のポイントは以下の通りです。
- 明確な役割分担: 各経営者の担当業務が明確に分かれており、重複していないことを証明する必要があります。例えば、「A氏は海外営業とマーケティング担当、B氏は国内の生産管理と財務担当」のように、それぞれの専門性が事業に不可欠であることを示さなければなりません。
- 事業規模: 複数の経営者を必要とするだけの事業規模や業務量があることを、事業計画書で説得力をもって示す必要があります。
- 資本金: 最も厳しい要件の一つです。原則として、ビザを申請する外国人経営者1人につき、500万円以上の出資が求められるケースが一般的です。つまり、2名で申請する場合は、合計1000万円の資本金が必要になる可能性が高いということです。
安易な共同経営は、「名義貸し」や「ビザ取得目的の偽装経営」を疑われるリスクが高いため、慎重な計画と専門家との相談が不可欠です。
Q2: 家族(配偶者や子供)を日本に呼ぶことはできますか?
A: はい、可能です。
あなたが経営管理ビザを取得すれば、あなたの法律上の配偶者とお子さんは「家族滞在」ビザを申請して、一緒に日本で暮らすことができます。
経営管理ビザの申請と同時に、ご家族の家族滞在ビザを申請することも一般的です。
ただし、重要な条件があります。
それは、あなたが家族全員を養えるだけの十分な経済力(扶養能力)を持つことです。
これは、あなたの会社の事業計画書に記載する役員報酬の額によって判断されます。
扶養する家族が増えれば、それだけ高い役員報酬を設定し、その報酬を支払えるだけの会社の収益見込みを示す必要があります。
また、お子さんの年齢が18歳を超えている場合、「扶養を受ける」というよりも「日本で働く」目的ではないかと疑われ、審査が厳しくなる傾向がある点にも注意が必要です。
Q3: 会社が赤字でもビザの更新はできますか?
A: 状況によりますが、1年目の赤字であれば可能性は十分にあります。
起業初年度は初期投資がかさむため、赤字になることは入国管理局も想定内です。
ただし、その場合は「なぜ赤字になったのか」という分析と「来期以降、どのように黒字化するのか」という具体的な事業改善計画書の提出が必須です。
危険なのは、2期連続の赤字や、会社の資産より負債が多い「債務超過」の状態です。
これらは事業の継続が困難であると判断され、更新が不許可になる可能性もあります。
Q4: 経営管理ビザで不許可になる最も一般的な理由は何ですか?
A: 多くの不許可事例には、共通するいくつかのパターンがあります。
- 事業所の不備: バーチャルオフィスや居住専用の物件を契約してしまったケース。事務所としての独立性や実態がないと判断されます。
- 資本金の出所不明: 500万円の出所や形成過程を、預金通帳の履歴などで客観的に証明できなかったケース。「見せ金」と疑われると一発でアウトです。
- 事業計画の具体性・実現性の欠如: 「何をどうやって売って、どう儲けるのか」という計画が曖昧で、夢物語だと思われてしまったケース。事業の継続性・安定性が認められません 82。
- 申請者本人の在留状況の問題: 過去にオーバーステイや資格外活動違反(例:留学生時代のアルバイトのしすぎ)など、日本のルールを守ってこなかった経歴がある場合、素行が不良と判断され、審査に悪影響を及ぼすことがあります。
これらの失敗例から学ぶべきは、入国管理局の審査が「形式」だけでなく「実質」を厳しく見ているという事実です。
Q5: 行政書士に依頼する必要はありますか?費用はどのくらいですか?
A: 法律上、申請を自分で行うことは可能ですが、専門家である行政書士に依頼することを強く推奨します。
経営管理ビザは、他の就労ビザと比べても格段に要件が複雑で、準備すべき書類も膨大です。審査官の裁量も大きく、どこが審査のポイントになるかを見極めるには専門的な知識と経験が不可欠です。
行政書士に依頼するメリット:
- 許可の可能性を高められる: 専門家は、あなたの状況におけるリスクを事前に洗い出し、それをカバーするための最適な書類作成や立証方法を提案してくれます。
- 時間と労力の節約: 複雑な書類作成や、平日の昼間にしか開いていない入国管理局への申請手続きを代行してもらえるため、あなたは事業の準備に集中できます。
- 精神的な安心感: 手続きのプロが伴走してくれることで、先の見えない不安が大幅に軽減されます。
行政書士への報酬は事務所によって異なりますが、新規で経営管理ビザを申請する場合、報酬額として20万円〜30万円程度が一般的な相場です。
これに加えて、会社設立のための登録免許税などの実費が別途かかります。
当法人の料金に関しては『会社設立とセットで経営管理ビザをお申込みの方へ』をご参照下さい。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
会社の設立や事業計画など、お金もかかるし作業も多くて大変だと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
経営管理ビザは他の在留資格の中でも難易度が高いと言われています。
しかし、きちんと実現性のある事業計画を建てて、安定して継続可能な事業を始めるということが伝えられる申請が出来れば、在留資格は付与されます。
特に以下の3点には注意が必要です。
- 信頼性のある事業計画: あなたの情熱とビジネスモデルを、具体的かつ論理的な言葉で語ること。
- 実体のある事業所: あなたのビジネスが根を張る、確固たる拠点を確保すること。
- 明確な事業資金: あなたの覚悟と事業の体力を、クリーンなお金の流れで証明すること。
これらの要件の一つ一つは、入国管理局があなたという経営者候補の「信頼性」と「本気度」を測るためのものです。
この記事が、経営管理ビザの取得を検討されている方への参考になりましたら幸いです。